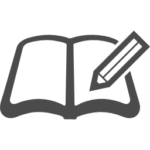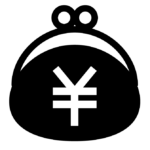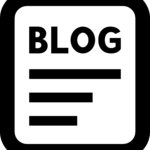個人情報の保護指針
山下司法書士事務所は,サービス提供のために必要な個人情報を取得します。これらの個人情報は,以下のように取り扱います。
- 関連法令・ガイドラインの遵守
当事務所は,以下の法律や規則を遵守して,皆様の個人情報を適切に取り扱います。
・個人情報保護法
・特定個人情報の利用に関する法律
・司法書士法
・その他関連法令
個人情報の保護に関する法律やガイドラインに基づき,情報の管理と取り扱いを行いますので,ご安心ください。
- 個人情報の取得について
当事務所は,適法かつ公正な方法で個人情報を取得します。具体的には,法律に従い,正当な手段を用いて情報を収集いたします。
- 個人情報の利用範囲について
(1)利用目的の範囲内での使用
当事務所は,個人情報を取得する際にお知らせした利用目的の範囲内でのみ,業務上必要な範囲において使用します。
(2)第三者への委託について
個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合,以下の措置を講じます。
・厳正な調査: 委託先について十分に調査します。
・適切な監督: 個人情報の安全を確保するために,必要な監督を行います。
- 個人情報の第三者への提供について
当事務所は,以下の方針で個人情報を取り扱います。
・同意なしでの提供禁止
法律で特別に定められている場合を除き,事前に本人の同意を得ることなく,個人情報(特定個人情報を除く)を第三者に提供することはありません。
- 個人情報および特定個人情報の管理について
(1)安全な管理
当事務所は,個人情報および特定個人情報を安全に管理します。
(2)安全管理措置
個人情報や特定個人情報の紛失,破壊,改ざん,漏えいを防ぐために,適切な安全管理措置を講じます。
(3)情報漏えいの防止
個人情報や特定個人情報の持ち出しや外部への送信に際して,情報が漏えいしないように徹底します。
- 保有個人データの開示・訂正・利用停止・消去について
(1)請求への対応
当事務所は,本人が自己の個人データについて開示,訂正,利用停止,消去などを請求できる権利を尊重し,これらの要求に対して誠実に対応します。
(2)利用目的の通知
本人から利用目的の通知を請求された場合,次の内容で対応します。
・手数料: 1件につき3,300円(税込)と郵送料の実費
・通知内容: 利用目的とともに通知します
ただし,以下の場合には開示しないことがあります。
・法令に基づく定め
・第三者の権利を害するおそれがある場合
・当事務所の業務に支障をきたす場合
その際は,理由を示して開示しない旨をお伝えします。
- 継続的改善について
当事務所は,以下のように継続的な改善に努めます。
・維持と改善
方針を維持しつつ,常に改善を行い,より良い運営を目指します。
・周知徹底
この方針を当事務所の職員や関係者にしっかりと周知し,理解を深めます。
- 特定個人情報の取り扱いについて
特定個人情報(行政手続きで特定の個人を識別するための番号など)は,利用目的が法律で制限されています。当事務所は,以下の方針で取り扱います。
・利用目的の限定
特定個人情報を,その目的を超えて取得または利用することはありません。
・第三者への提供禁止
法律で認められている場合を除き,特定個人情報を第三者に提供することはありません。
苦情申出先
山下司法書士事務所
担当 司法書士 山下弘樹
連絡先 026-293-2630
制定 平成26年12月
改定 令和6年9月6日
登記手続・裁判書類作成の受任内容(委任契約 定型約款)
受任者(甲) 山下司法書士事務所(司法書士 山下弘樹)
上記司法書士に登記・裁判書類作成を依頼する者(以下「委任者」)は、上記司法書士を受任者(以下「甲」)として、下記のとおり委任するための契約(約款)に同意をします。
- 甲の受任する内容(受任内容)
(1)法務局や裁判所その他官庁公署に登記、名義変更、訴状の提出その他必要な申請・届出をすること
(2) 戸籍謄本など、上記申請・届出に必要な書類を市区町村役場等の官庁公署から収集すること
(3)上記申請・届出に必要な書類を作成すること - 委任者は、この受任に必要な委任事務(以下「仕事」)に対する対価や準備の費用として、次の金銭を払ってください。
(1) 見積書、請求書の金額、または甲が指定した着手金。
(2) 戸籍謄本や住民票をとるために書類1通ごとに、金3,300円(税込)の報酬。
ただし、取得手数料や送料などの実費は別に必要です。
(3) 仕事に必要な実費・交通費。
(4) 仕事が完了したときや途中で一区切りついたときに交付した精算書、請求書の精算金額。 - 委任者は、仕事を始める前か途中で、本人確認にかかる証明書(免許証等)の甲への提示、コピーまたは提出する依頼があった場合には,従わなければなりません。
- 預かった金銭の精算は、仕事が完了したときか、手続に必要な書類の準備が整ったときまたは、委任が終了したときに行います。
- 支払いが遅れた場合には、支払いが完了するまで、甲はこの仕事を始めないか、仕事を途中で中止することができます。仕事を途中で中止することになっても、請求した費用のうち、かかった分(進捗状況に従った報酬と実費)は、すぐに支払ってもらいます。
- 委任者、甲どちらにも責任がなく、仕事を途中で中止することになった場合には、お互いに話しあった上で、仕事にかかった費用(必要費、実費等)を精算します。甲だけに大きな責任があって、仕事を途中で中止したときには、受け取った金銭は実費を差し引いてお返しします。甲に責任がないのに委任者の責任により(故意または重大な過失)、仕事を中止せざるを得なくなったときには、甲は請求した費用(報酬・実費)の全額から、かかっていない実費を差し引いて請求します。
- 請求した費用を委任者が支払わないときは、甲は委任者から預かっている書類等を返却しないことができます。また、甲はそのときに預かっている金銭を費用と差し引き(相殺)できます。
- 以下にあげたことが発生したときは、この契約を取りやめます(解除)。その場合には、甲の責任は、ないことにします(免責)。
(1) 委任者が甲の仕事の妨害をした場合。
(2) 委任者が甲の受けている他の委任事務(事件)のもう一方の当事者だったときや、甲が受けている他の委任事務や依頼が、委任者のためにならないこと(利益相反)がわかったとき、その他この契約の仕事をすることによって、甲が他の業務を公正にできなくなってしまうおそれがあるとき。
(3) 委任者が書類を集めることや打ち合わせ、調整を依頼したにもかかわらず、そのまま6か月間放置したとき。 - 委任者が、甲から依頼した書類取得等の協力を6か月以上遅らせた場合や、請求した費用を支払わなかった場合には、預かった書類は連絡の上、連絡がとれなかったときには何も告げずに返却することがあります。
- 登記や申請手続が完了したら、この仕事に関わる、法務局やその他の官庁公署から発行された権利書(登記識別情報)や預かった書類については、なるべく早く返却します。
- 書類の返却は甲の事務所で行うか、委任者の住所に普通郵便か書留郵便、レターパック等で送付します。
- 書類を返却するために、 本人確認をした住所へ郵便を出しても宛名人不明や受け取り拒否等で戻ってきてしまった場合には、委任者に断らずに書類を破棄することがあります。
- この契約は、第9項から第12項にある書類の返却や破棄によっても終了します。
- 仕事に関わる不動産や物件について、仕事の原因となっている契約に不適合があったり、損害が生じたとしても、甲は、責任を追わないことに同意します。
令和元年7月6日作成
令和3年2月26日修正
預り金規程
当事務所は,司法書士等による預り金管理に対する社会的関心および信頼確保の重要性を踏まえ,依頼者からお預かりする預り金について,その適正かつ厳格な管理を確保することを目的として,本規程を定めます。
第1条(目的)
本規程は,当職(山下司法書士事務所の司法書士,以下同じ)が業務上預かる金銭(以下「預り金」という。)の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規程における「預り金」とは,依頼者等から業務の遂行にあたり一時的に預かった金銭をいう。
第3条(預り金の管理)
- 預り金は,当職の固有財産と明確に区分し,適切に管理しなければならない。
- 預り金は,預かり金額や依頼の態様に応じて,次に掲げる方法を用いて管理する。ただし,預り金専用口座には,全額が預金保護制度(ペイオフ)対象の決済用預金口座を利用するものとする。
(1)耐火金庫
(2)事業用口座
(3)預り金専用口座(以下「預り金口座」という。) - 現金で預り金を受領した場合は,以下のとおり管理する。
(1)現金は,原則として少額に限り,耐火金庫により厳重に保管する。
(2)受領額が50万円以下であって,かつ1週間以内に出金または精算が見込まれる場合に限り,耐火金庫での保管を行うことができる。
(3)上記以外の場合(例:50万円を超える現金の受領等)には,速やかに事業用口座に入金し,他の資金と分別して管理する。 - 現金による預り金については,依頼者または成年後見人ごとに明確に区分して個別に管理する。
- 100万円以上の預り金を1か月を超えて保有する場合には,必ず預り金口座を利用して保管・管理するものとする。
- 遺産整理業務または財産管理業務に関する預り金については,預り金口座を用いて管理する。
第4条(預り金履歴の開示)
- 預り金の状況については帳簿に正確に記録し,依頼者等からの問い合わせがあった際には,その内容を開示しなければならない。
- 事件終了後1年を過ぎた預り金履歴の開示は,記録を7年以内のみ開示するものとし,手数料として1件3,300円(税込)及びコピー実費を請求する。
- 依頼者に相続,解散等があった場合はその一般承継人または承継法人に開示及び返還の権利を有するものとする。ただし,一般承継人または承継法人がその権利を証するため,相続関係説明図,戸籍謄本,遺産分割協議書その他承継を証する書類の提示を求めることができる。
第5条(預り金の入出金と返還)
- 預り金は,業務中においては,その業務の性質に従って依頼者に確認し,または依頼者の委任の範囲で適正に入出金を行う。
- 預り金は,業務の完了または中止に伴い速やかに依頼者またはその権利を有する者に返還しなければならない。
- 現金の返還に際しては,必要に応じて返還記録を作成し,依頼者の同意を得るものとする。
- 預り金の精算記録の確認は,精算書または業務の領収書の引き渡しによって行う。
- 依頼者等から預り金の返還に際して依頼者等名義の振込先口座の指定がある場合には,振込手数料を差し引いて振込により返還することができる。
第6条(帳簿の整備)
- 預り金に関する入出金履歴は,法令及び当職が定める基準に従い正確かつ明瞭に記録し,帳簿を整備しなければならない。
- 帳簿及び関連書類は7年間保存するものとする。
第7条(分別管理の義務)
- 預り金は,当職の固有資産と明確に分別して管理しなければならない。財産管理,遺産整理業務における預り金もこれに準ずる。
- 後見人の金銭を預貯金や有価証券で管理する場合は,被後見人の預貯金口座または被後見人と後見人の名義が併記された口座等で管理しなければならない。
- 遺産整理業務,財産管理業務において預り金の依頼者別管理が困難なほど重複している場合には,新たに預り金口座を開設して管理しなければならない。
第8条(業務不能時の対応体制)
- 当職が心身上の理由により業務を行えなくなる事由が発生した場合に備え,補助者及び相続人が依頼者の預り金の円滑な払い戻し及び精算を行えるよう,必要な体制を整備しなければならない。
- 前項の事由が発生した場合,依頼者および一般承継人は,依頼者であることを証明するため,運転免許証等の身分証明書を提示して権利を行使するものとする。
第9条(規程の改定及び監査)
- 預り金の管理に関しては,次のとおり監査を行う。
(1)現金の入出金については,都度,記録を確認し監査を行う。
(2)事業用口座および預り金口座については,1か月ごとに自己点検を行い,6か月ごとに監査を実施する。
(3)後見業務等において管理する財産については,家庭裁判所の指示および公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの定める規則に従って,定期的な監査を受けるとともに,リーガルサポートからの随時監査の要請に応じて,速やかに帳簿等の提示を行わなければならない。 - 監査は,当職が入出金を行った場合には補助者が,補助者が入出金を行った場合には当職が行うものとする。ただし,補助者が行った口座の入出金については,都度当職が確認を行う。
第10条(教育及び継続的改善)
- 預り金の適正な管理を維持するため,当職および補助者は,法令,規則,および本規程に基づく運用に関する知識と技能の維持・向上に努め,必要に応じて研修その他の教育を受けなければならない。
- 本規程に定める運用状況については,定期的に見直しを行い,問題点を把握し,改善策を講じることで,継続的な管理体制の改善を図るものとする。
第11条(規程の改定)
本規程の改定は,当職の責任において行い,必要に応じて依頼者に通知するものとする。
令和7年5月16日作成