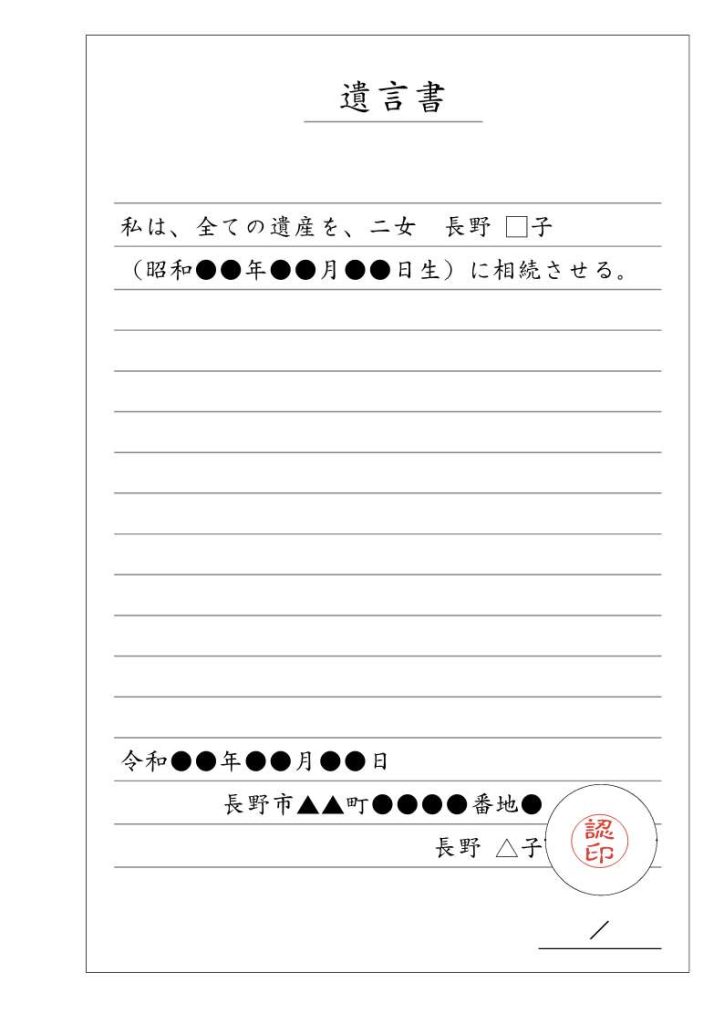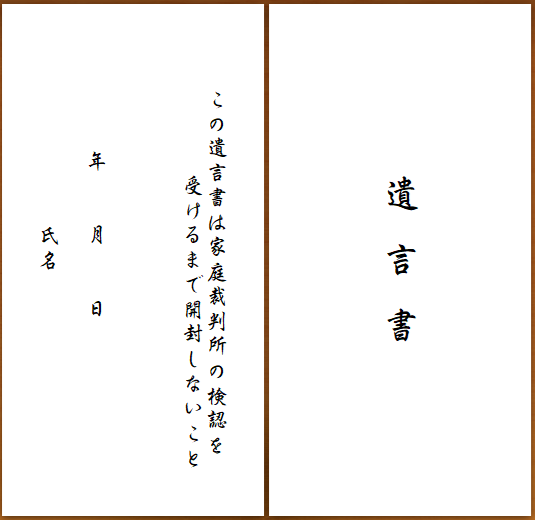空き家特例の概要
相続した空き家を売却する際に適用できる「空き家特例」は,父または母が居住していた土地・建物を売却した場合に,所得税の譲渡所得について特別控除が認められる制度です。
(国税庁「相続した空き家を売却した場合の特例 チェックシート」)
空き家増加と特例の注目
空き家が増加傾向にあるようで,将来の売却を見据えて空き家特例の適用を前提とした名義変更を相談される方も増えてきています。
(参考:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)
注意点
特例の可否判定を十分に検討せずに名義変更をしてしまうと,後から修正することが困難な場合が多いです。
特に「更正登記や再遺産分割協議で是正できないか」との相談が寄せられますが,実際には救済されないケースが多いようです。
裁判例や実務の指摘
専門家となる税理士とよく相談の上で検討する必要があります。
更正登記や再遺産分割協議をしても特例が認められないケースが多いことが指摘されています。
(参考:税法好きAIお嬢(オタク)の実務ノート「【判例×実務】東京地裁R6.9.2判決と空き家特例——譲渡前の『抹消・再登記』で特例適用の余地」)
専門家に相談を
空き家特例を見据えて売却を予定する場合は,国税庁チェックシートで一次確認を行い,必ず税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
名義変更と売却の順番と設計が重要であり,一度進めた手続を後から更正しても救済されないことが多いため,事前の全体の設計で失敗を防ぐようにしましょう。