誤解が多いのですが、複数ページの書類の押印と同じ印影を各ページの書面と書面の間に押印するものが「契印」です。
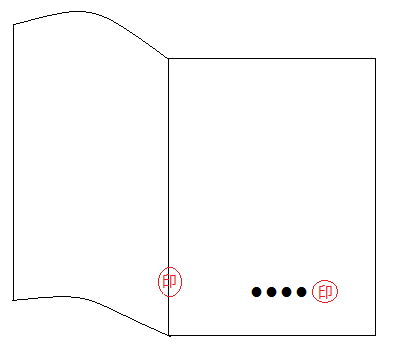
書類について、別の書類に押印して、控えを保存しておくものが「割印」です。
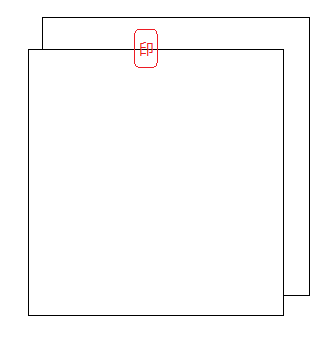
しかしながら、わかりやすさから、契印を割印ということが多いのはしかたのないことです。
誤解が多いのですが、複数ページの書類の押印と同じ印影を各ページの書面と書面の間に押印するものが「契印」です。
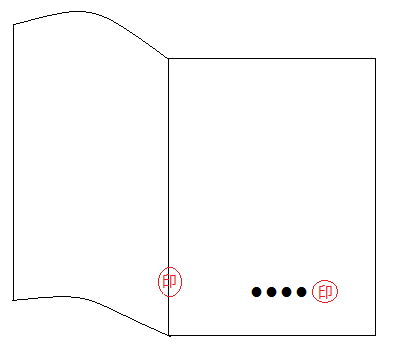
書類について、別の書類に押印して、控えを保存しておくものが「割印」です。
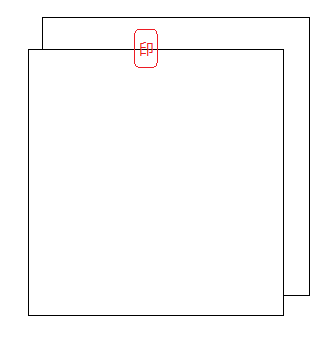
しかしながら、わかりやすさから、契印を割印ということが多いのはしかたのないことです。
全く、協力関係のない会社からリンクされることもあります。
「社畜る」というサイトなんですが、
以下、上記サイトから転記
山下司法書士事務所
「https://www.syachi9.black/service_list/nagano-touki/」「社畜る:会社設立登記代行・長野県(松本 上田 飯田 佐久 信濃)の手数料も印紙も含めて0円~ 参照」
最安値のサービス:書類チェック5,000円
設立年月日:昭和47年
契約社数:不明
所在地:長野市篠ノ井布施五明249番地3
コメント:土地建物の名義変更の手続を安心して任せられます。
相続財産や相続人を把握し、円滑な相続手続きをサポートします。
http://yamashitashiho.com/
設立年月日があっていません。
弊所の設立は、平成26年です。どこからこの設立年月日をもってきたのかわかりません。
料金も、他の基本サービスを外して、最安値サービスが記入されています。他の司法書士の料金もそうだと思いますが、基本サービス以外のオプション料金を最安値サービスとしているみたいです。
サイトを作成したかたの品性を少し疑ってしまう事例でした。
結構、検索されています。
今日は、「立木」の登記についてはなしをします。
ホームページに誰が訪問されたかは、よくわかりませんが、
どんな検索ワードを訪問していただいたかは、知ることができます。
検索された中でも多いのは、「立木」と「懲戒場」です。
そこで、一応立木の登記について、申請書の書き方の一部をメモしておきます。
----------------------------------
登記の目的 立木所有権保存
所有者 ●番地
A
添付情報
住所証明情報 立木図面 承諾情報(土地に担保権がある場合)
申請書副本
令和年月日 立木に関する法律第16条第1項第1号申請
●●地方法務局 御中
課税価格 ●円(税務上の時価)
登録免許税 ●円(上記価格の4/1000)
立木の表示
不動産番号
所 在 長野市●
地 番 ●番
地 目 山 林
地 積 ●平方メートル
樹 種 すぎ(ひらがな)
数 量 ●平方メートル ●本
樹 齢 ●年生
調査年度 令和●年
-----------------------------
ところで、長野県内だけかもしれませんが、オンラインでの登記事項証明書の取得とかできません。オンラインでの申請もできません。書面での申請となります。
立木図面の作成と課税価格の計算が難しそうですね。
会社を作ったまま、放置していると、登記懈怠のの過料制裁(罰金みたいなもの)が課される恐れがあります。
毎年株主総会や取締役会を行っている会社であればいいのですが、
特に個人事業や仲間内の事業で法人化した会社の場合、
取締役の任期について、考えていない場合があります。
以前の商法改正や会社法改正等によって、取締役の法律上の任期が変化しています。
このことが、任期の考え方を一層難しくしているのです。
実は、監査役にも同じことがいえ、古くからある株式会社で、監査役が選任したままの場合、辞任の登記しないまま放置できるのは、最高でも10年が上限です。
また、時代による選任時期によっても上限があります。
参考 「監査役の法定任期の変遷(改訂版)」(司法書士内藤卓氏)
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/67534227b7673b04c701b98bc980393a
会社の取締役と監査役の任期を長期的に把握することが必要なのですね。
登記申請で、申請書を作成する場合には、現在ではソフトを使うことが多いです。
事務所で普段利用している登記用のソフトは、純粋に「総合申請ソフト」を利用してします。純粋というのは、市販のソフトはいろいろあるのですが、法務省から出されていて無料で使えるものということを意味します。
市販のソフトは、いい面が多く、いろいろな申請書の書式があることと、登記の情報をインターネットからダウンロードして、それを申請書に反映することができます。
しかしながら、市販のソフトは、価格も専用ソフトのため高額ですし、運用するにも費用がかかります。
総合申請ソフトで、申請書の物件表示欄だけでも、反映できないかと、自作で過去に、登記情報を登記申請に変換するソフトを作りました。(Windowsのバッチファイルで)
そして、最近では、物件表示欄の中でも敷地権の表示のある区分建物を反映できるように改良しました。
せっかく作ったので、区分建物の仕事がくるとうれしいです。
後見人の面会の頻度は、どのくらいがいいのでしょうか。
面会の頻度のはなしをします。
司法書士や弁護士さんの士業による被後見人への面会はどのくらいの頻度が一般的なんでしょうか。
1か月?2か月?または、そんなにあってられない?
例えば親族が病院に入院している場合には、その頻度もさまざまでも、どちらかといえば、その親族との距離感が頻度につながっているようです。
聞くところによると、家族であれば、週1回以上のかたもいるし、年に1回も来られないかたもいるらしいです。
当然、頻度は多ければ多いほど、患者や施設利用者にとってはいいはずです。家族や近しい人の力があってこその治療や生活になるわけですから。
士業の場合は、家族でもないのでそのあたり難しいですよね。
多ければ多いほど信頼関係は厚くなりそうですが。
この前に、被後見人さんに質問されました。
今日は、ソーシャルワーカー(社会福祉士)さんと
後見人との役割の違いを話します。
ソーシャルワーカーさんは、
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うこと
(社会福祉士及び介護福祉士法 第2条参照)
後見人は、
被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務
(民法第858条)
被後見人の財産の管理及び代表
(民法第859条)
ざっくりいうと
ソーシャルワーカーさんは、生活の相談
後見人は、財産の管理
と伝えました。
被後見人にとってみれば、誰がどんな役割をしているのか
わかりにくいようです。
クレームの理由の多くは、業務の放置だそうです。
今日は、仕事の放置のはなしをします。
司法書士は登記、供託や訴訟に関するさまざまな業務をしていますが、仕事をするなかで、加盟している司法書士会に業務上での苦情が何件かきているようです。
苦情にもっとも多いと報告されているのが、仕事の放置です。
依頼を受けても、適切な期間で処理していなかったり、説明がなかったり、ほとんど進めていないこともあるようです。
仕事が進まない理由には、その事件の背景等、さまざまなことが考えられますが、なぜ、やらなければならない仕事を説明のないまま放置されるといったことが起きてくるのでしょうか。
仕事が放置される最大原因は、仕事の属人化です。
仕事が人にぶらさがっているため、仕事を受けた人の体調や精神状態、能力に大きく左右されるからです。
属人的な仕事ほど、その人の仕事の進め方に影響を受けてしまい、仕事の遅延や放置というリスクを伴います。
会社などの法人で仕事を受けた場合で、業務をシステマチックに運ぶような仕組みづくりをしていれば、たとえ成員のひとりが仕事を放置していても、他の者が仕事を進めてくれるので、自然に仕事が進むようになります。
法人で仕事を受ける場合は、未然に放置を防ぐ機能を果たせるようになっているのです。
しかしながら、司法書士の場合は、業務のほとんどが属人的な仕事であり、たとえ法人格があっても、勤務者の数が少なかったりするため、その仕組みを活用しにくくなっています。
たとえ法人でなくとも、事務的な仕事を受ける際には、事務所内で属人化している仕事を補える仕組みづくりをしていかなければなりません。
登記情報が電子化後の合併でした。
長野市にも平成の大合併でいくつかの
行政区画が合併になりました。
そのうちの一つに大岡村があって、
今回始めてその場所の登記情報を取得したところ、
表示登記部分が変更されていました。
それで、自己の最近作成した登記情報を
登記申請書に変換するプログラムが対応しておらず、
すべて旧の大岡村に変換されてしまう始末。
急いで修正しました。
修正するにしても、土地、建物、敷地権なし区分建物と
敷地権付区分建物の4種類を直さなければならず、
手間のかかる作業でした。
前回から作成していた、プログラムについて、
課題をいくつかを解決させました。
1.区分建物と敷地権付区分建物に対応
2.PDFから直接変換できるようにした
3.共同担保目録の変換(共同担保が1つの場合のみ)
プラットホームはWindowsのみでDOSプロンプトを使用しています。
登記申請書のXMLはUTF-8で、DOSはShiftJISなので
文字変換を中に組み込んでいます。
Shift JIS→Unicode→UTF8
と変換してします。
今後の課題は、
1.複数の共同担保目録の対応
2.多数の区分建物に対応させる
3.権利者or義務者の挿入に対応
3は、いろいろなパターンがあるので難しいかもしれません。